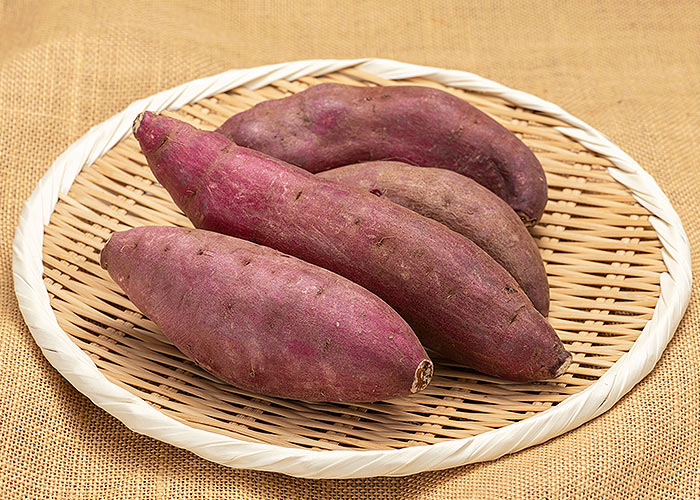秋の味覚の代表格、さつまいも。ほくほくとした甘さは格別ですが、食べた後のおならが気になってしまう、という方も少なくないのではないでしょうか。実は、さつまいもでおならが出るのには、消化されにくい「でんぷん」や豊富な「食物繊維」といった、はっきりとした理由があるのです。この記事では、その科学的な原因を解き明かすとともに、おならを気にせず美味しく楽しむための5つの対策を具体的にご紹介します。嬉しいことに、さつまいもによるおならは臭いにくく、むしろ腸が元気に働いている証拠とも言えます。食べ合わせや調理の工夫で、悩みを解消しながら、さつまいもの健康効果を最大限に引き出しましょう。
さつまいもでおならが出るのは本当?その原因を解説

秋の味覚として多くの人に愛される、さつまいも。あのほくほくとした食感と優しい甘さは、どこか心を和ませてくれます。しかし、その一方で「さつまいもを食べるとおならが出やすくなる」という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。これは単なる言い伝えや気のせいではなく、実はしっかりとした科学的な理由に基づいています。ここでは、さつまいもがおならの原因となるメカニズムを詳しく解説していきます。
原因1 消化されにくい「でんぷん」と腸内細菌
さつまいもの主成分である「でんぷん」。実は、このでんぷんの一部は、私たちの体内の消化酵素では分解されにくい性質を持っています。通常、食べ物に含まれるでんぷんは、唾液や膵液に含まれるアミラーゼという消化酵素によって糖に分解され、小腸で吸収されます。しかし、さつまいもに含まれる一部のでんぷんはこの分解を免れ、そのまま大腸へとたどり着くのです。
大腸には、私たちの健康を支える多種多様な腸内細菌が暮らしています。大腸に届いた消化されにくい「でんぷん」は、この腸内細菌、特に善玉菌にとって格好のエサとなります。善玉菌はこれを喜んで分解(発酵)し、その過程で水素や二酸化炭素、メタンといったガスを発生させます。このガスが腸内に溜まり、おならとして体外に排出されるというわけです。つまり、さつまいもによるおならは、腸内細菌が元気に活動している証拠とも言えるのです。
原因2 豊富な「食物繊維」がガスを発生させる
さつまいもが「食物繊維の宝庫」であることは、よく知られています。食物繊維もまた、おならが出やすくなる大きな要因の一つです。食物繊維は、人の消化酵素では分解できず、でんぷんと同様に大腸まで届きます。
さつまいもには、水に溶けやすい「水溶性食物繊維」と、水に溶けにくい「不溶性食物繊維」の両方がバランス良く含まれています。このうち、特に水溶性食物繊維は、腸内で善玉菌のエサとなりやすく、発酵する過程でガスを発生させます。不溶性食物繊維は便のカサを増やして腸を刺激し、お通じをスムーズにする働きが主ですが、これも腸の動きを活発にさせるため、結果としてガスが排出されやすくなることにつながります。
このように、さつまいもに含まれる「消化されにくい性質を持つ成分」が、おならの主な原因となっているのです。
| 原因となる成分 | 腸内での働き | 結果 |
|---|---|---|
| 消化されにくい「でんぷん」 | 大腸で善玉菌のエサとなり、発酵する | 水素、二酸化炭素などのガスが発生する |
| 豊富な「食物繊維」(特に水溶性) | 大腸で善玉菌のエサとなり、発酵する | ガスが発生し、腸の動きも活発になる |
さつまいものおならは臭いにくいって本当?

「さつまいもを食べた後のおならは、回数は増えるけれど臭いはきつくない」という話を聞いたことはありませんか。実は、これもまた事実である可能性が高いのです。
おならの強烈な臭いの元となるのは、主に悪玉菌が肉や魚、卵といった動物性タンパク質を分解する際に発生する、硫化水素やインドール、スカトールといった腐敗物質です。これらは、いわゆる「腐った卵のような臭い」や「便の臭い」の原因となります。
一方で、さつまいもが原因で発生するガスの主成分は、前述の通り、善玉菌がでんぷんや食物繊維といった炭水化物を分解して作る水素や二酸化炭素です。これらのガス自体には、ほとんど臭いがありません。そのため、さつまいもだけを食べた場合に発生するおならは、臭いが少ない傾向にあると言えます。もしおならの臭いが気になる場合は、腸内環境が乱れて悪玉菌が優位になっているか、タンパク質の多い食事との組み合わせが影響しているのかもしれません。
さつまいもを食べてもおならを出にくくする5つの対策
さつまいもがおならの原因になりやすいのは事実ですが、少しの工夫でその心配を大きく減らすことができます。せっかくの美味しいさつまいもですから、お腹の張りを気にせず楽しみたいものですよね。ここでは、毎日の食生活に手軽に取り入れられる5つの対策をご紹介します。どれも簡単な方法ばかりですので、ぜひ試してみてください。
対策1 皮ごとゆっくりよく噛んで食べる

さつまいもを食べる時、何気なく皮を剥いてしまっていませんか。実は、さつまいもの皮とそのすぐ内側には、おなら対策に役立つ成分が豊富に含まれています。その代表が「ヤラピン」という成分です。ヤラピンは胃腸の働きを活発にし、便通をスムーズにしてくれる効果が期待できます。腸内に便が溜まる時間が短くなれば、それだけガスの発生も抑えられます。
また、食事の基本ではありますが、「ゆっくりよく噛むこと」も非常に重要です。唾液に含まれる消化酵素「アミラーゼ」が、さつまいものでんぷんを分解する第一歩を担ってくれます。よく噛んで細かくすることで、胃腸での消化吸収がスムーズになり、腸内での異常発酵を防ぐことにつながるのです。
対策2 食べ合わせを工夫する
さつまいも単体で食べるのではなく、一緒に食べるものを選ぶ「食べ合わせ」も、おなら対策にはとても有効です。腸内環境を整えたり、消化を助けたりする食材を組み合わせることで、さつまいものデメリットをカバーし、メリットをさらに引き出すことができます。
乳製品や発酵食品で腸内環境を整える

ヨーグルトやチーズといった乳製品、そして味噌や納豆などの発酵食品には、ビフィズス菌や乳酸菌などの「善玉菌」が豊富に含まれています。さつまいもの食物繊維は、これらの善玉菌にとって格好のエサとなります。善玉菌が優勢な腸内環境では、ガスを過剰に発生させる悪玉菌の働きが抑えられ、お腹の張りが起こりにくくなります。さつまいもとヨーグルトを和えたサラダや、具材の一つとしてさつまいもを使ったお味噌汁などは、手軽で美味しいおすすめの組み合わせです。
消化を助ける大根やりんごと一緒に食べる

特定の食材に含まれる「消化酵素」の力を借りるのも賢い方法です。例えば、大根には「ジアスターゼ」というでんぷん分解酵素が含まれており、さつまいもの消化を直接的に助けてくれます。また、りんごに含まれる水溶性食物繊維「ペクチン」は、腸内の善玉菌を増やし、腸の動きを穏やかに整える働きがあります。
| 一緒に食べると良い食材 | 期待できる効果と食べ方の例 |
|---|---|
| 大根 | でんぷん分解酵素「ジアスターゼ」が消化を促進します。熱に弱い性質があるため、大根おろしとして焼き芋に添えるのがおすすめです。 |
| りんご | 水溶性食物繊維「ペクチン」が腸内環境を整えます。さつまいもとりんごを一緒に煮たり、サラダに加えたりすると美味しくいただけます。 |
| ヨーグルト | 豊富な乳酸菌がさつまいもの食物繊維をエサにして増え、腸内フローラのバランスを改善します。マッシュしたさつまいもと混ぜてサラダにするのも良いでしょう。 |
対策3 調理方法を工夫して消化しやすくする

同じさつまいもでも、調理の仕方ひとつで消化のしやすさは大きく変わってきます。ガスを発生させにくくするためには、でんぷんをできるだけ分解しやすい形にしてあげることがポイントです。
じっくり加熱してヤラピンを増やす
対策1でも触れた「ヤラピン」は、さつまいもを切った時に断面から染み出る白い液体で、加熱することで量が増えると言われています。また、さつまいもは低温でじっくりと時間をかけて加熱することで、でんぷんが糖に変わり、甘みが増すだけでなく消化にも良い状態になります。ご家庭では、炊飯器の玄米モードで蒸したり、オーブンで低温調理したりする「焼き芋」や「蒸し芋」が、おなら対策には最適な調理法と言えるでしょう。
一度冷やしてレジスタントスターチを増やす

少し意外に思われるかもしれませんが、加熱したさつまいもを一度冷やすことも有効な対策です。さつまいもは冷える過程で、でんぷんの一部が「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」という成分に変化します。このレジスタントスターチは、小腸で消化されずに大腸まで届き、食物繊維のように善玉菌のエサとなって腸内環境を整える働きをします。結果として、ガスの発生を穏やかにしてくれる効果が期待できるのです。冷やし焼き芋や、一度冷ましてから作るポテトサラダなどがおすすめです。
対策4 一度にたくさん食べ過ぎない
これはさつまいもに限った話ではありませんが、どんなに体に良い食材でも、一度に大量に摂取すれば消化器官に負担がかかります。特に食物繊維が豊富なさつまいもは、食べ過ぎると消化が追いつかず、腸内でガスが溜まる直接的な原因となってしまいます。美味しいからとついつい手が伸びてしまいますが、1食あたりの量はこぶし1個分程度を目安にするなど、適量を心がけることが何よりの対策です。
対策5 ガスを排出しやすくするハーブティーを飲む

ガスの発生を抑えるだけでなく、発生してしまったガスを体外へスムーズに排出する手助けをするのも一つの方法です。一部のハーブには、お腹の張りを和らげたり、ガスの排出を促したりする「駆風作用」があるとされています。さつまいもを食べた後や、お腹が張って苦しいと感じる時に、温かいハーブティーを飲むと、心も体もリラックスできるでしょう。
| ハーブティーの種類 | 期待できる効果 |
|---|---|
| ペパーミントティー | メントールの清涼感が特徴で、胃腸の働きを整え、消化を助けると言われています。お腹のガス抜きをサポートしてくれます。 |
| カモミールティー | リラックス効果で知られ、ストレスによる胃腸の不調を和らげるのに役立ちます。腸の痙攣を鎮め、穏やかに作用します。 |
| フェンネルティー | 古くから消化促進や駆風のために利用されてきたハーブです。独特の甘い香りがあり、お腹の張りを解消する効果が期待できます。 |
さつまいもだけじゃない おならが出やすくなる食べ物
さつまいもを食べるとおならが出やすくなるのは、特有の成分による自然な体の反応です。実は、私たちの身の回りには、さつまいも以外にも同じような働きを持つ食べ物がたくさん存在します。これらの食べ物と原因となる成分を知っておくことで、ご自身の体調やその日の予定に合わせて食事をコントロールしやすくなるでしょう。おならの原因となりやすい食べ物の多くは、腸内環境を整える上で大切な役割を持っていますので、むやみに避けるのではなく、上手に付き合っていくことが大切です。
ここでは、おならが出やすくなる代表的な食べ物をご紹介します。
豆類(大豆、あずきなど)

豆類は、健康的な食材として知られていますが、同時におならの原因になりやすい食べ物の代表格でもあります。その主な原因は、豆類に豊富に含まれる「オリゴ糖」にあります。特に「ラフィノース」や「スタキオース」といった種類のオリゴ糖は、人間の消化酵素では分解されにくいため、そのまま大腸まで届きます。そして、大腸にいる腸内細菌がこれらのオリゴ糖をエサとして分解する際に、水素やメタンなどのガスが発生するのです。これは、腸内細菌が活発に働いている証拠でもあります。大豆やあずきはもちろん、煮豆や納豆、豆腐といった加工品も同様です。
芋類(じゃがいも、里芋など)

さつまいもと同じ芋の仲間たちも、おならが出やすくなることがあります。じゃがいもや里芋、長芋なども、さつまいもと同様にでんぷんや食物繊維を多く含んでいます。これらの成分が消化の過程で腸内細菌によって発酵され、ガスを発生させるメカニズムはさつまいもと共通しています。特に、じゃがいもを調理後に冷やすと、さつまいもと同じように消化されにくい「レジスタントスターチ」が増えるため、食物繊維と似た働きをしてガスの原因となることがあります。
食物繊維が豊富なごぼうやきのこ類

食物繊維が豊富と聞くと、体に良いイメージが強いかもしれません。実際にその通りなのですが、種類によってはガスが発生しやすくなるものもあります。例えば、ごぼうや玉ねぎ、にんにくなどに多く含まれる水溶性食物繊維の一種「イヌリン」は、腸内で発酵しやすく、ガスの原因となることがあります。また、きのこ類や海藻類に豊富な不溶性食物繊維も、腸の動きを活発にする過程で、腸内に溜まっていたガスが排出されやすくなることがあります。これらは腸のぜん動運動を促し、便通を整えるために欠かせない働きをしています。
おならが出やすくなる食べ物と、その原因となる主な成分を下の表にまとめてみました。ご自身の食生活を振り返る際の参考にしてみてください。
| 食べ物の種類 | 主な原因成分 | 具体的な食品例 |
|---|---|---|
| 芋類 | でんぷん、食物繊維、レジスタントスターチ | さつまいも、じゃがいも、里芋、こんにゃく芋 |
| 豆類 | オリゴ糖(ラフィノース、スタキオースなど) | 大豆、あずき、ひよこ豆、レンズ豆、納豆 |
| 穀物類 | 食物繊維、糖質 | 玄米、麦、オートミール、全粒粉パン |
| 野菜類 | 食物繊維(イヌリンなど) | ごぼう、玉ねぎ、にんにく、キャベツ、ブロッコリー |
| きのこ・海藻類 | 食物繊維 | しいたけ、えのき、しめじ、わかめ、昆布 |
| 果物・乳製品 | 果糖、乳糖(ラクトース) | りんご、バナナ、洋梨、牛乳、ヨーグルト |
このように見てみると、多くの健康的な食品が名を連ねていることがお分かりいただけるでしょう。おならは体からの自然なサインであり、これらの食品が腸内でしっかり働いてくれている証拠ともいえるのです。
おならは健康の証拠 さつまいもの嬉しい健康効果
さつまいもを食べるとおならが出やすくなるのは、裏を返せばそれだけ腸が活発に動いている証拠ともいえます。おならを気にするあまり、栄養満点のさつまいもを避けてしまうのは、非常にもったいないことかもしれません。実は、さつまいもには私たちの体にとって嬉しい健康効果がたくさん詰まっているのです。ここでは、おならの向こう側にある、さつまいもの素晴らしいパワーについてご紹介します。
便秘の解消をサポート

さつまいもが便秘解消に良いとされる理由は、主に二つの成分にあります。それが「食物繊維」と、さつまいも特有の成分である「ヤラピン」です。
さつまいもには、水に溶けやすい「水溶性食物繊維」と、水に溶けにくい「不溶性食物繊維」の両方がバランス良く含まれています。水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなって腸内環境を整え、不溶性食物繊維は便のカサを増やして腸を刺激し、スムーズな排便を促してくれます。
さらに、さつまいもを切ったときに出てくる白い液体「ヤラピン」は、胃腸の働きを活発にし、便を柔らかくする効果が期待できる成分です。この「食物繊維」と「ヤラピン」の相乗効果こそが、さつまいもが便秘解消の強い味方といわれる所以なのです。
美肌作りやアンチエイジングに

さつまいもは、美しく健やかな肌を保ちたい方にとっても、ぜひ取り入れたい食材です。肌のハリを保つコラーゲンの生成を助けたり、シミの原因となるメラニンの生成を抑えたりする「ビタミンC」が豊富に含まれています。
一般的にビタミンCは熱に弱い性質がありますが、さつまいものビタミンCはでんぷんに守られているため、加熱しても壊れにくいという大きな特長があります。
また、「若返りのビタミン」とも呼ばれる強い抗酸化作用を持つ「ビタミンE」や、体内でビタミンAに変わり皮膚や粘膜を健康に保つ「β-カロテン」も含まれています。これらの成分が複合的に働くことで、肌の老化を防ぎ、若々しい印象を保つ手助けをしてくれるでしょう。
生活習慣病の予防
さつまいもに含まれる栄養素は、美容だけでなく、生活習慣病の予防にも役立つことが期待されています。特に注目したいのが、「カリウム」と「食物繊維」です。
カリウムには、体内の余分なナトリウム(塩分)を体外へ排出する働きがあります。これにより、血圧の上昇を抑える効果が期待でき、高血圧の予防に繋がります。塩分の多い食事を摂りがちな私たち日本人にとっては、非常に重要なミネラルです。
また、豊富な食物繊維は、糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急激な上昇を防ぐ働きがあります。これは糖尿病の予防にも繋がる大切なポイントです。さつまいもが持つ主な健康効果を下の表にまとめました。
| 栄養素 | 期待される主な健康効果 |
|---|---|
| 食物繊維 | 便秘解消、血糖値の上昇抑制、コレステロール値の低下 |
| ヤラピン | 腸のぜん動運動促進、便を柔らかくする |
| ビタミンC | 美肌効果、抗酸化作用、免疫力向上 |
| ビタミンE | 抗酸化作用(アンチエイジング)、血行促進 |
| カリウム | 高血圧予防、むくみ改善 |
| アントシアニン(紫芋) | 眼精疲労の回復、抗酸化作用 |
おならは気になるかもしれませんが、それは腸が元気に働いているサインです。さつまいもが持つこれらの素晴らしい健康効果を、ぜひ日々の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
まとめ

さつまいもを食べるとおならが出やすくなるのは、消化されにくい「でんぷん」や豊富な「食物繊維」を腸内細菌が分解する際に、ガスが発生するためでした。これは腸が活発に動いている証拠であり、私たちの体が持つごく自然な働きなのです。また、さつまいもが原因のおならは臭いがきつくなりにくいという嬉しい側面もあります。どうしても気になる場合は、皮ごとよく噛んだり、大根やりんごといった消化を助ける食材と組み合わせたり、じっくり加熱したりと、食べ方に少しの工夫をこらすことで穏やかにできるでしょう。便秘解消や美肌作りにも役立つさつまいもを、これからも安心して美味しく味わっていきたいものですね。