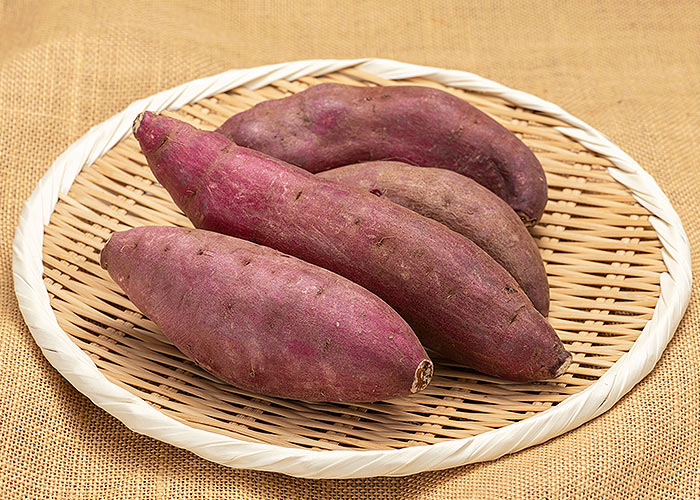春の訪れとともに薄着の季節が始まると、冬に蓄えた体脂肪が気になりはじめ、「さつまいもダイエット」を始める人も増えてきます。甘みがあって満足感も高く、食物繊維が豊富なさつまいもは、健康的に痩せたい人にとって心強い味方です。ところが、間違った食べ方をすると、便秘が悪化することも。腸に優しいイメージのあるさつまいもですが、不溶性食物繊維が多く含まれるため、水分不足や食べ過ぎは便の硬化や排便トラブルの原因になりかねません。この記事では、さつまいもを美味しく食べながら便秘を防ぐコツをわかりやすく紹介します。
さつまいもダイエットするにはぴったりな季節?

一年を通して最も過ごしやすい季節といわれる春。しかし近年は、「桜が咲いた」と思ったら、あっという間に初夏のような暑さが訪れることが増えてきました。まるで季節が駆け足で進んでしまうような感覚で、気づけば薄着の季節が目前に迫っており、心も体も準備が追いつかない、そんな声もよく耳にします。思い返せば、今冬は何度も記録的な寒波に見舞われ、「暖冬」と言われがちな最近の冬とは一線を画す、非常に厳しい寒さが続きました。冷え込む日が多く、着込むことが当たり前になっていた時期をようやく抜け出し、春の気配がようやく感じられるようになってきた今、気になるのが「冬に蓄えてしまった脂肪」。寒さに備えるためとはいえ、重ね着で何とかごまかせていた体型も、薄着になる春夏シーズンには隠しきれなくなってしまいます。

そんな季節の変わり目に、多くの人が考えるのが「ダイエット」。五島商店佐藤の芋屋が運営するオウンドメディアでも、ダイエット関連の記事は一年を通して高い人気を誇ります。特に、さつまいもを取り入れた健康的なダイエット法や、手軽に始められる焼き芋ダイエットの記事は注目度が高く、アクセス数も安定しています。
季節の変わり目に体調を整えながら、無理なく始められるダイエット法を探している人にとって、さつまいもを活用したダイエットは、自然と注目が集まるテーマとなっているようです。春からの新しい生活に向けて、少しずつ体も気持ちも整えていきたいですね。因みにこの辺りのさつまいも・焼き芋ダイエット記事が人気です。

焼き芋ダイエットを行う場合は、主食の代わりに取り入れるのが効果的です。ごはんやパンを焼き芋に置き換えたからといって、大幅にカロリーを抑えられるわけではありませんが、食物繊維の含有量は圧倒的に多く、消化の過程にも良い影響を与えます。特に、不溶性と水溶性の食物繊維がバランスよく含まれているため、腸の動きを促し、老廃物の排出をスムーズにする働きが期待できます。腸内環境が整うことで、体の代謝も向上しやすくなり、健康的に体重を管理しやすくなるため、ダイエットを目的とする場合は、ごはんやパンの代わりに積極的に取り入れるとよいでしょう。
詳しくはこちら

さつまいもを使った置き換えダイエットのポイントとして、主食をさつまいもに置き換える、皮ごと食べる、冷やして食べるなどがあります。特に夜の食事にさつまいもを取り入れると、カロリー消費が少ない時間帯でも体脂肪の蓄積を防ぎやすくなります。消化器官への負担も軽減され、食欲のコントロールがしやすくなるでしょう。夜の置き換えダイエットは、総カロリー摂取量の削減に効果的です。さつまいもを取り入れることで、健康的に体重を減らしやすくなります。
詳しくはこちら

さつまいもは糖質が多いと敬遠されがちですが、実際にはダイエットに適した食材です。特に注目したいのは、低GI値による血糖値の安定化と豊富な食物繊維です。これにより、食後のインスリン分泌が抑えられ、脂肪の蓄積を防ぐ効果が期待できます。また、ビタミンCやカリウムも豊富に含まれており、美容や健康維持にも役立ちます。さつまいもをうまく取り入れることで、ダイエットを効率的に進めることが可能です。
詳しくはこちら
さつまいもダイエットで本気でダイエットに挑戦!と思うのですが、さつまいもダイエットで注意しないといけないことがあります。今回は、さつまいもダイエット、さつまいもを食べる時に注意する点を紹介します。間違ったさつまいもダイエットやさつまいもの食べ方をするとダイエット中に起こる「便秘」がさらにひどい状態になり、ダイエットをしているのに体重もむくみも増加しちゃう恐れもありますので…さつまいもダイエット、さつまいもを食べる時の注意点を守ってトライしてみてくださいね。
さつまいもは便秘に良いと言われますが(食物繊維)
さつまいもは便秘に良いとよく言われますが、その理由として真っ先に挙げられるのが、豊富に含まれる食物繊維です。中でも「便秘の特効薬」とまで呼ばれることもあり、多くの人が日常的に取り入れやすい食材として注目しています。

実際に、さつまいもには食物繊維がしっかりと含まれています。たとえば、皮をむいて蒸した場合、100gあたりの食物繊維量は約2.3gとされています。しかし、皮ごと蒸した場合にはその量が大きく変わり、100gあたり3.8gもの食物繊維が含まれるという結果が出ています。この違いは見逃せません。皮付きのまま調理した方が、より多くの食物繊維を摂取できるというわけです。
こうした数値を見ると、「食物繊維が豊富=便秘に効く」というイメージが強くなりがちです。けれども、食物繊維には実は2種類があり、それぞれに異なる役割と働きがあります。ひとつは「不溶性食物繊維」、もうひとつは「水溶性食物繊維」です。この2つのバランスが腸内環境に与える影響を左右し、便秘の改善にどのように貢献するかが変わってきます。さつまいもが便秘に良いとされる理由も、ただ単に「食物繊維が多いから」というだけではなく、どのような種類の食物繊維が、どのくらい含まれているかを知ることがとても大切です。
さつまいもの不溶性食物繊維

不溶性食物繊維は、便のかさを増やし、腸のぜん動運動を活発にする働きがあります。これにより、腸内をスムーズに通過しやすい状態へと整え、自然な排便を促す助けとなります。ただし、摂取量が多すぎると腸の中で便が硬くなりやすく、逆に詰まりやすくなることもあります。特に水分が不足していると、腸内で食物繊維がうまく膨らまず、かえって便秘が悪化する可能性もあるため注意が必要です。
さつまいもの水溶性食物繊維

水溶性食物繊維は、腸内で水分を吸収してゲル状に変化し、便に適度な柔らかさと潤いを与える働きがあります。これによって、便の滑りがよくなり、排便時の負担が軽減されやすくなります。また、腸内の善玉菌の栄養源となるため、腸内フローラのバランスを整えやすくなり、結果として腸の状態を健やかに保つ助けとなります。腸への刺激が穏やかで、毎日のお通じが気になる人や便秘がちな人にとって、特にオススメの成分といえます。
さつまいもの食物繊維量の割合は?

さつまいもに含まれる食物繊維は、「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の二つの種類から構成されています。この2種類の食物繊維は、それぞれ異なる働きを持ち、腸内環境や便通に対して異なるアプローチで作用します。まず、皮をむいて蒸したさつまいもの場合、100gあたりの総食物繊維量は約2.3gです。その内訳を見ると、不溶性食物繊維が約1.7g、水溶性食物繊維が約0.6gとなっており、全体の中では不溶性食物繊維の割合がやや多いことがわかります。
一方で、皮付きのまま蒸したさつまいもの場合、100gあたりの食物繊維量は3.8gまで増加します。このうち、不溶性食物繊維は2.8g、水溶性食物繊維は1.0gと、どちらも皮なしの状態よりも多く含まれており、特に不溶性食物繊維の量が大きく増える傾向があります。このように、さつまいもは皮ごと調理することで、より多くの食物繊維を摂取できることになります。特に不溶性食物繊維を意識して取り入れたい場合には、皮ごとの調理が効果的といえます。もちろん、水溶性食物繊維も含まれており、腸内の善玉菌のエサとなったり、便をやわらかくしたりといった働きも期待されます。
さつまいもを食べて便秘にならない食べ方

さつまいもには「便秘に良い」というイメージを持つ方が多いかもしれませんが、実際には注意が必要な点もあります。というのも、さつまいもに含まれる食物繊維は、思っている以上に「不溶性食物繊維」の割合が高く、人によってはその働きが腸に合わず、逆に便秘を引き起こしてしまうことがあるからです。
不溶性食物繊維は、便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促す作用がある一方で、水分が不足していたり、摂りすぎたりすると、腸内で便が硬くなり詰まりやすくなるという側面もあります。さつまいもでダイエットに挑戦しようと思っていたのに、かえって便秘になってしまっては本末転倒です。ダイエット中の便秘は代謝の低下やむくみ、肌荒れにもつながりやすいため、できるだけ避けたいものです。そこで、さつまいもを美味しく食べながら、便秘を引き起こさないためのちょっとした工夫や食べ方のコツを押さえておくことが大切です。体にやさしく、腸にも負担をかけずにさつまいもを取り入れるためには、食べ合わせや調理方法、水分の摂り方など、いくつかのポイントがあります。
次にご紹介するのは、さつまいもを食べても便秘になりにくくするための、実践しやすい方法やコツです。日々の食生活に上手に取り入れながら、さつまいもの力を無理なく引き出していきましょう。
さつまいもと一緒に水分を摂る

先ほども触れましたが、さつまいもには不溶性食物繊維が多く含まれており、腸内で水分を吸収しながら膨らみ、便のかさを増やす働きがあります。この作用によって腸が刺激され、排便が促されるのが特徴ですが、同時に注意しておきたいのが「水分不足」の状態です。体内の水分が不足したまま不溶性食物繊維を摂取すると、腸の中で便が必要以上に硬くなり、逆に排出しにくくなってしまう恐れがあります。
もちろん、さつまいもには水溶性食物繊維も含まれており、便をやわらかくしたり、腸内環境を整える働きにもつながっています。ただし、どちらの種類の食物繊維においても、水分がなければその力を十分に発揮できません。特にさつまいもを使ったダイエットを行う場合、ふかし芋や焼き芋といった調理法で食べる機会が多くなりますが、その際は意識して水分をしっかりと摂るよう心がけることが大切です。

目安としては、さつまいもを食べる前後に常温の水や温かいお茶などを1~2杯飲む習慣をつけると良いでしょう。冷たい水は一気に体を冷やしてしまうことがあるため、胃腸の働きを妨げないよう、なるべく常温か温かい飲み物を選ぶのがおすすめです。
水溶性食物繊維を含む食品と組み合わせる

さつまいもに含まれる食物繊維には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方があり、このバランスが腸内環境に良い影響を与えるとされています。もともと、さつまいもは腸内の調子を整えやすい食品として知られていますが、より一層スムーズな排便や腸内フローラの健全化を目指すのであれば、さらに水溶性食物繊維が豊富な食材を組み合わせて取り入れると、効果が感じやすくなります。

たとえば、海藻類は水溶性食物繊維が非常に豊富な食材のひとつです。わかめや昆布などは日常的に使いやすく、味噌汁などに加えるだけでも簡単に取り入れることができます。さつまいもを使ったダイエット中の食事の中でも、朝食や昼食に「わかめ入り味噌汁」を組み合わせるだけで、腸にやさしい食事へとぐっと近づきます。
さらに味噌は、言わずと知れた発酵食品であり、乳酸菌や酵母などが豊富に含まれています。これらの菌が腸内の善玉菌をサポートし、腸内バランスの向上にひと役買ってくれます。つまり、さつまいもに加えて海藻、そして発酵食品である味噌を取り入れることで、ダイエットと腸活、さらに便秘対策までもが一度に行える、非常に理想的な組み合わせとなります。
さつまいもは冷やして食べる

さつまいもダイエットでさつまいもを食べて便秘にならないようにするには焼いたり蒸したりした後に一度冷ましてから食べる方法がおすすめです。加熱直後のさつまいもに含まれるでんぷんは、冷やすことで構造が変化し、一部が「レジスタントスターチ」と呼ばれる消化されにくい成分に変わります。このレジスタントスターチは小腸では消化されずに大腸まで届き、腸内細菌によって発酵されることで、善玉菌を増やす短鎖脂肪酸(酪酸や酢酸など)を作り出します。
短鎖脂肪酸には腸内環境を整えたり、腸の炎症を抑えたり、免疫の働きを高めたりする効果があるとされており、便秘の予防や改善にもつながります。さつまいもを日常的に取り入れながら腸の調子を整えたいときや、甘みを楽しみながら健康的に食べたいときには、冷やし焼き芋や冷やしふかし芋といった食べ方がとても効果的です。
さつまいもは適量を守って食べる

さつまいもは、「さつまいもダイエット」という方法で実際に成果を上げたという有名人も多く、糖質がやや高めであるにもかかわらず、ダイエット向きの食材として広く認識されるようになりました。また、腸内環境を整える食材としても知られており、食物繊維が豊富に含まれている点がその人気を支えています。甘みがありながらも自然な素材であることから、ダイエット中の満足感を得やすい食材として注目され続けています。
一方で、いくら健康的な印象があるからといって、過剰に摂取してしまうと注意が必要です。さつまいもに多く含まれる不溶性食物繊維は、腸を刺激して便通を促す働きがありますが、体質や食べる量、水分摂取の状況によっては、逆に便が硬くなって排出しにくくなったり、便秘が悪化するというケースも見られます。
特に、短期間で痩せたいという思いから、主食の代わりに大量のさつまいもを一気に摂るような食べ方は、腸への負担が大きくなりやすく、思わぬ不調を引き起こす原因になることもあります。便秘だけでなく、ガスの発生や腹部の張りといった症状にもつながる可能性があるため、さつまいもを取り入れる際は、量とバランスに意識を向けることが重要です。
まとめ

春の訪れとともに注目が高まるさつまいもダイエットですが、体にやさしい印象とは裏腹に、便秘を悪化させてしまうケースもあります。その理由は、さつまいもに豊富に含まれる不溶性食物繊維の影響。水分不足や食べ過ぎによって、便が硬くなり排出しづらくなる可能性があるため、腸に合った食べ方を心がけることが大切です。水分をしっかりと摂る、海藻や味噌といった腸活に適した食材と組み合わせる、ダイエットで使うさつまいもは冷やして食べる、そして適量を守る。この4つのポイントを押さえておけば、さつまいもの栄養を活かしながら、無理なく便秘予防とダイエットを両立することができます。さつまいもを正しく取り入れて、これからの季節を軽やかにスタートさせましょう!