
さつまいもには多種多様な品種がありますが、「人気がない」と言われる品種は本当に存在するのでしょうか?実は明確に不人気な品種があるわけではなく、食感のトレンドや流通量、栽培の難しさといった理由で、私たちの目に触れる機会が少ないだけなのです。この記事では、定番から希少品種までの特徴を網羅的に解説。それぞれの品種が持つ隠れた魅力や美味しい食べ方、あなたにぴったりの一品を見つけるための選び方が分かります。
まずは知っておきたい人気のさつまいも品種とその特徴
「さつまいも」と一言で言っても、その品種は多種多様。品種によって甘さや食感が大きく異なり、それぞれに最適な食べ方があります。「人気の無い品種」を知る前に、まずは現在市場の主流となっている人気のさつまいも品種を知ることで、ご自身の好みの基準が明確になります。ここでは、食感のタイプ別に代表的な人気品種とその魅力をご紹介します。
ねっとり甘い高糖度系の人気さつまいも品種
近年の焼き芋ブームを牽引しているのが、この「ねっとり系」です。時間をかけてじっくり加熱することで、まるでスイーツのような濃厚な甘さと、蜜が溢れ出すほどのクリーミーな食感が生まれます。そのままで極上のデザートになる、まさに現代のさつまいもトレンドの主役です。
紅はるか

「紅はるか」は、他の品種よりも「はるか」に甘く、美味しいことからその名が付けられました。加熱後の糖度は非常に高く、強い甘みにもかかわらず後味はすっきりとしているのが特徴です。焼き芋にすると、黄金色の果肉から蜜がじゅわっと溢れ出し、しっとりとなめらかな食感を楽しめます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な産地 | 鹿児島県、茨城県、千葉県など |
| 旬の時期 | 10月~1月頃(貯蔵により長く出回る) |
| 食感 | ねっとり、しっとり |
| 甘さ | 非常に強い |
| おすすめの食べ方 | 焼き芋、干し芋、スイートポテト |
安納芋

ねっとり系の代表格として不動の人気を誇るのが「安納芋」です。種子島の特産品として知られ、水分が多く粘質性が高いため、加熱するとクリームのようにネットリとした食感に変化します。水分が多く、糖度が高いのが特徴です。カロテンを豊富に含むため果肉は鮮やかなオレンジ色をしており、その濃厚な甘さと風味は一度食べたら忘れられないほどのインパクトがあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な産地 | 鹿児島県(種子島) |
| 旬の時期 | 10月~1月頃 |
| 食感 | 非常にねっとり、クリーミー |
| 甘さ | 非常に強い |
| おすすめの食べ方 | 焼き芋、ペーストにしてお菓子作り |
しっとり滑らかな食感で人気のさつまいも品種
「ねっとり」と「ほくほく」のちょうど中間に位置するのが「しっとり系」です。滑らかな舌触りと上品な甘さが特徴で、バランスの取れた味わいが人気を集めています。焼き芋はもちろん、様々な料理やお菓子作りにも使いやすい万能さが魅力です。
シルクスイート

2012年に登場した比較的新しい品種ながら、瞬く間に人気品種の仲間入りを果たしたのが「シルクスイート」です。その名の通り、絹(シルク)のようになめらかな舌触りと、上品な甘さが最大の特徴。収穫してすぐはやや粉質ですが、貯蔵して熟成させることで水分が増し、よりしっとりとした食感と甘みに変化します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な産地 | 千葉県、茨城県、熊本県など |
| 旬の時期 | 9月~12月頃 |
| 食感 | しっとり、なめらか |
| 甘さ | 強い |
| おすすめの食べ方 | 焼き芋、スイートポテト、蒸し芋 |
昔ながらのほくほく食感が人気のさつまいも品種
ねっとり系がブームとなる前から、さつまいもの定番として愛されてきたのが「ほくほく系」です。水分が少なく粉質で、加熱すると栗のようにホクホクとした食感になります。上品な甘さで煮崩れしにくいため、天ぷらや大学芋、煮物といった料理に最適です。根強いファンを持つ、日本の食卓に欠かせない存在です。
鳴門金時

西日本を代表するブランドさつまいもが「鳴門金時」です。徳島県の鳴門市周辺の、水はけの良い砂地で栽培されています。栗のようにホクホクとした食感と、品の良い甘さが特徴で、鮮やかな紅色の皮と黄金色の果肉という美しい見た目も人気の理由です。煮崩れしにくく、素材の味を活かす料理によく合います。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な産地 | 徳島県 |
| 旬の時期 | 8月~11月頃 |
| 食感 | ほくほく、粉質 |
| 甘さ | 上品な甘さ |
| おすすめの食べ方 | 天ぷら、大学芋、ふかし芋、味噌汁の具 |
紅あずま

東日本で「さつまいも」と言えば、この「紅あずま」を思い浮かべる方も多いでしょう。関東地方を中心に広く栽培されており、スーパーでも手に入りやすい定番品種です。繊維質が少なく、加熱すると黄色が濃くなり、粉質でほくほくとした昔ながらの食感が楽しめます。甘みと食感のバランスが良く、焼き芋から料理まで幅広く活躍します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な産地 | 茨城県、千葉県など |
| 旬の時期 | 9月~11月頃 |
| 食感 | 強いほくほく感 |
| 甘さ | やや強い |
| おすすめの食べ方 | 焼き芋、天ぷら、大学芋、煮物 |
「人気がない」と言われるさつまいも品種は本当に存在するのか
スーパーの店頭では「紅はるか」や「安納芋」といった特定の人気品種ばかりが目立ちますが、一方で「人気がない」と言われるさつまいもは本当に存在するのでしょうか。結論から言うと、味や品質が劣るから人気がない、という単純な話ではありません。実際には、時代の食のトレンドの変化、特定の用途に特化していること、あるいは栽培の難しさから流通量が極端に少ないことなどが理由で、私たちの目に触れる機会が少ない品種がたくさんあります。
ここでは、「人気がない」と言われるさつまいもが、どのような背景を持っているのかを3つの視点から詳しく解説します。
時代の変化で見かけなくなった昔ながらの品種

かつては食卓の主役だったにもかかわらず、時代の流れとともに見かける機会が減ってしまった品種があります。これらの品種は、現代主流の「ねっとり系」とは異なる、素朴で優しい甘さやほくほくとした食感が特徴です。
例えば、「太白(たいはく)」や「源氏(げんじ)」といった品種は、かつて焼き芋や天ぷらなどで親しまれていました。しかし、より甘味が強く、しっとりとした食感の「紅はるか」などの新品種が登場したことで、消費者の好みが変化し、次第に生産量が減少していきました。病気に弱かったり、収穫量が安定しなかったりすることも、生産者が作付けを減らす一因となっています。決して美味しくないわけではなく、食感や甘さのトレンドから外れてしまったために、表舞台から遠ざかっているのです。
用途が限定される加工用のさつまいも品種
私たちが普段、青果として目にすることはないものの、加工食品の世界では絶大な需要を誇るさつまいも品種があります。これらは特定の用途に最適化されており、一般的な焼き芋や蒸し芋には向かないため、スーパーに並ぶことはほとんどありません。
しかし、それぞれの分野では「大人気」であり、日本の食文化を支える重要な存在です。代表的な加工用さつまいも品種を下の表にまとめました。
| 品種名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| コガネセンガン(黄金千貫) | 本格芋焼酎、でんぷん | でんぷん質が非常に豊富で、芋焼酎特有の華やかな香りと風味を生み出す。焼酎原料としては不動の人気を誇る。 |
| シロユタカ | でんぷん、春雨 | 病気に強く収量が多い。でんぷん含有率が高く、食品工業用のでんぷん原料として広く利用されている。 |
| アヤムラサキ | 食品着色料、お菓子、野菜パウダー | 鮮やかな紫色のもとであるアントシアニン色素が豊富。天然の着色料として加工食品やスイーツに欠かせない存在。 |
このように、コガネセンガンがなければ美味しい芋焼酎は生まれず、アヤムラサキがなければ紫芋スイーツの美しい色は出せません。一般消費者にとって馴染みがないだけで、専門分野では不可欠な品種なのです。
栽培が難しく流通量が少ない希少品種

非常に美味しいと評価されながらも、栽培の難しさや特定の地域でしか生産されていないために、市場にほとんど出回らない「幻の品種」も存在します。これらの品種は生産量が極めて少ないため、見つけること自体が困難です。
- 七福(しちふく):強い甘みと滑らかな食感が特徴ですが、つる割れ病に非常に弱く、安定して栽培するのが難しい品種です。そのため、生産者が限られ、希少価値が高まっています。
- 隼人芋(はやといも):鹿児島県の一部で栽培される在来種。ゴツゴツとした見た目で調理しにくい面もありますが、独特の風味とねっとり感があり、地元では根強い人気があります。
- 種子島ゴールド(たねがしまゴールド):「種子島紫」とも呼ばれる紫芋の一種。安納芋と同じ種子島で栽培され、強い甘みと鮮やかな紫色が特徴ですが、安納芋に比べて生産量が少なく、希少な品種とされています。
これらの品種は、人気がないのではなく、生産量が需要に追いつかない、あるいは販路が限定されているために入手が難しいというのが実情です。もし直売所や通販などで見かけることがあれば、それは非常に幸運な出会いと言えるでしょう。
さつまいも品種の人気を左右する3つの理由
私たちが普段スーパーマーケットで目にするさつまいもの品種は、実は数ある品種の中のほんの一部です。では、なぜ特定の品種ばかりが人気を集め、店頭に並ぶのでしょうか。その背景には、単なる「味」だけではない、消費者のトレンド、流通の都合、そして生産者の事情が複雑に絡み合った3つの大きな理由が存在します。
理由1 食感と甘さのトレンド
さつまいもの人気を語る上で最も影響力が大きいのが、時代の求める「食感」と「甘さ」のトレンドです。特に近年の焼き芋ブームは、品種の勢力図を大きく塗り替えました。
現代の主流は「ねっとり系」

現在のさつまいも人気の中心にいるのは、間違いなく「ねっとり系」と呼ばれる高糖度の品種です。代表格である「紅はるか」や「安納芋」は、加熱すると蜜が溢れ出すほどの強い甘みと、まるでクリームのように滑らかな食感が特徴です。このスイーツ感覚で楽しめる濃厚な甘さとクリーミーな食感が、デザートとしてさつまいもを求める現代の消費者のニーズに合致し、絶大な支持を集めています。特に焼き芋にした際の満足感は格別で、専門店が増えたことも人気を後押ししています。
料理によっては「ほくほく系」が優れることも

一方で、昔ながらの「ほくほく系」品種の人気が衰えたわけではありません。鳴門金時や紅あずまに代表されるこれらの品種は、上品な甘さと粉質で崩れやすい食感が特徴です。この特性は、料理に使う際に大きなメリットとなります。例えば、天ぷらにすれば衣がべたつかずカラッと揚がり、大学芋や煮物にすれば味が染み込みやすく、煮崩れした食感がまた美味しさを引き立てます。料理の用途によって品種の適性が異なり、根強い需要があるため、今でも多くの家庭や料理店で愛用されています。
| 食感のタイプ | 代表的な品種 | 特徴とおすすめの調理法 |
|---|---|---|
| ねっとり系 | 紅はるか, 安納芋, シルクスイート | 糖度が高く、水分が多い。加熱するとクリーミーな食感になる。焼き芋やスイートポテト、干し芋など、素材の甘さを活かす調理に向いている。 |
| ほくほく系 | 鳴門金時, 紅あずま, 高系14号 | 水分が少なく粉質。加熱するとほくほくとした食感になる。天ぷら、大学芋、煮物、味噌汁の具など、調理後も形を保ちたい料理に適している。 |
理由2 流通のしやすさと見た目
どんなに美味しいさつまいもでも、消費者の手元に届かなければ人気は生まれません。スーパーマーケットなどの小売店に並ぶまでには、「流通」という大きなハードルがあり、ここでの都合が品種の人気を大きく左右します。
スーパーに並びやすい形の均一性

多くの消費者がさつまいもを購入するスーパーでは、商品の「見た目」が非常に重要です。皮の色が鮮やかで、形が紡錘形に整っている品種は、見栄えが良く、消費者が手に取りやすくなります。また、大きさが揃っていると箱詰めの効率が上がり、輸送コストを抑えることができます。見た目の美しさと規格の揃えやすさが、大規模流通の鍵となり、結果として店頭に並ぶ機会が増え、人気品種としての地位を確立しやすくなるのです。
貯蔵性の高さと旬の長さ
さつまいもは収穫後、一定期間貯蔵することでデンプンが糖に変わり、甘みが増すという特性があります。この「追熟」の期間を含め、長期間品質を保てる「貯蔵性」の高い品種は、流通業者にとって非常に価値があります。貯蔵性が高ければ、収穫期が過ぎても安定して市場に供給し続けることが可能です。長期間安定して市場に供給できる貯蔵性の高さは、販売期間の長さにつながり、消費者が一年を通して購入できる「定番の品種」となるための重要な要素です。
理由3 栽培の難しさと生産量
最終的に、さつまいもの人気は「どれだけ作られているか」という生産量に直結します。生産者である農家が「作りたい」と思える品種でなければ、市場に十分な量が出回ることはありません。
病気に強く育てやすい品種が好まれる
農業は常に病気や害虫のリスクと隣り合わせです。さつまいも栽培においても、「つる割病」や近年問題となっている「基腐病(もとぐされびょう)」など、収穫量に大きな影響を与える病気が存在します。これらの病気に耐性を持つ品種は、農薬の使用を減らせるだけでなく、収穫がゼロになるリスクを低減できるため、生産者にとって非常に魅力的です。栽培の手間やリスクが少ない品種は、生産者が積極的に作りたがるため、作付面積が広がり、結果的に流通量が増えて私たちの食卓に届きやすくなります。
収穫量が安定しないと市場に出回りにくい
農家の経営を考えると、単位面積あたりの収穫量、すなわち「収量性」も極めて重要な指標です。どんなに味が良く、希少価値があったとしても、収穫量が少なければ採算が合わず、商業的な栽培は難しくなります。天候不順などの影響を受けにくく、毎年安定して一定量の収穫が見込める品種は、生産計画を立てやすく、経営の安定につながります。収量の安定性が、生産者の経営を支え、市場への安定供給を可能にするため、結果として主要な人気品種として定着していくのです。
実は美味しい!隠れた魅力を持つさつまいも品種とその食べ方
スーパーマーケットの店頭に並ぶのは、流通量が多く人気も安定している品種が中心です。しかし、世の中にはまだまだ知られていない、隠れた魅力を持つさつまいもがたくさんあります。ここでは、特定の調理法で輝きを放つ品種や、昔ながらの素朴な味わいが楽しめる品種など、一味違ったさつまいもの世界をご紹介します。
料理に使いやすい甘さ控えめの品種
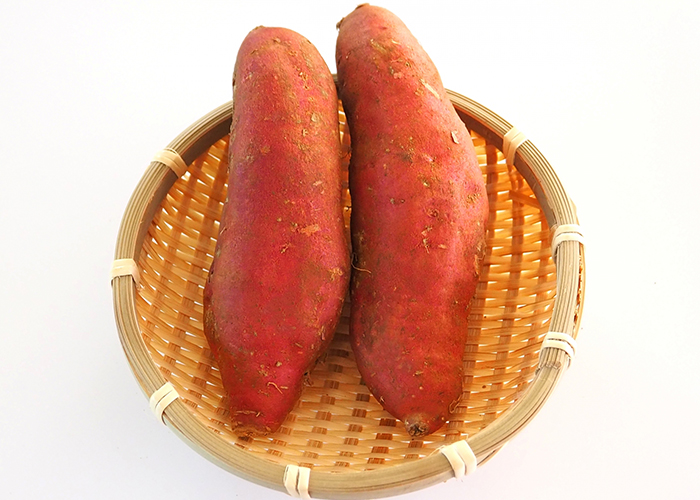
「さつまいも料理は甘くなりすぎるのが苦手…」と感じる方もいるのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが、上品な甘さで野菜のように使える品種です。これらのさつまいもは、煮物や炒め物、サラダなど、毎日の食卓のおかずとして大活躍します。強い甘みがないからこそ、他の食材の味を引き立て、料理全体のバランスを整えてくれる名脇役なのです。
| 品種名 | 特徴 | おすすめの食べ方 |
|---|---|---|
| 高系14号(こうけいじゅうよんごう) | 「鳴門金時」や「紅あずま」の親にあたる品種。上品な甘さと、煮崩れしにくい粉質の肉質が特徴。 | 天ぷら、大学芋、レモン煮、煮物全般。特に天ぷらにすると、衣はサクッと、中はほっくりとした食感が楽しめます。 |
| 人参芋(にんじんいも) | β-カロテンが豊富で、果肉が鮮やかなオレンジ色。甘さは控えめで、野菜に近い風味を持つ。 | ポタージュスープ、きんぴら、かき揚げ、サラダ。彩りが美しいので、料理のアクセントになります。 |
例えば、高系14号で大学芋を作ると、べたっとせず、芋本来のほくほく感と上品な甘さを味わえます。人参芋のポタージュは、自然な甘みと美しいオレンジ色で、食卓を華やかに彩ってくれるでしょう。
素朴な味わいが魅力の昔ながらの品種
ねっとり系の甘いさつまいもが主流になる以前は、水分が少なく、栗のようにほくほくとした食感の品種が親しまれていました。生産量の減少から今ではあまり見かけなくなりましたが、その素朴で奥深い味わいは根強いファンを持っています。派手さはありませんが、噛みしめるほどに広がる優しい甘みと香りは、現代の品種にはない、どこか懐かしい魅力に満ちています。
| 品種名 | 特徴 | おすすめの食べ方 |
|---|---|---|
| 太白(たいはく) | 皮も果肉も白い、粉質で水分が少ない品種。栗を思わせるような、ほくほくとした食感と風味を持つ。 | ふかし芋、焼き芋、コロッケ、マッシュポテト。シンプルな調理法で、芋本来の素朴な美味しさが際立ちます。 |
| 兼六(けんろく) | 石川県の伝統野菜。上品な甘みと強いほくほく感が特徴で、煮崩れしにくい。 | 煮物、おでんの具、味噌汁の具。じっくり煮込むことで、出汁の旨味と芋の甘みが調和します。 |
太白をじっくり時間をかけて焼き芋にすると、水分が飛んで凝縮された甘みと、ほろほろと崩れるような食感が楽しめます。まさに「昔ながらの焼き芋」を体験できるでしょう。
お菓子作りに最適な紫芋などのカラフルな品種

さつまいもの魅力は味や食感だけではありません。紫やオレンジといった鮮やかな色を持つ品種は、お菓子作りにおいてその真価を発揮します。これらの品種は、アントシアニンやβ-カロテンといった色素成分を豊富に含んでおり、見た目の美しさだけでなく栄養価の面でも注目されています。天然の色素を活かせば、着色料を使わなくても、いつものお菓子が格段に華やかな仕上がりになります。
| 品種名 | 特徴 | おすすめの食べ方 |
|---|---|---|
| パープルスイートロード | 紫芋の中では甘みが強く、食感も比較的しっとりしているため加工しやすい。加熱しても色が抜けにくい。 | スイートポテト、モンブラン、ペーストにしてパンに練り込む。鮮やかな紫色が美しいスイーツが作れます。 |
| アヤコマチ | 鮮やかなオレンジ色の果肉が特徴。加熱後の変色も少なく、甘みが強い。 | プリン、チーズケーキ、パウンドケーキ。かぼちゃのような感覚で使え、美しい黄金色のスイーツになります。 |
| 種子島ゴールド | 「種子島紫」とも呼ばれる紫芋。アントシアニンが豊富で、加熱すると鮮やかな紫色になる。 | さつまいもチップス、かりんとう、餡(あん)。甘さは控えめな傾向があるため、砂糖を加えて調整しやすいのも魅力です。 |
パープルスイートロードでモンブランを作れば、そのビビッドな紫色でゲストを驚かせることができるでしょう。アヤコマチのプリンは、その美しいオレンジ色と濃厚な甘みで、子どもから大人まで喜ばれる一品になります。
珍しいさつまいも品種と出会う方法
スーパーの店頭に並ぶさつまいもは、流通量が多く人気の品種が中心です。しかし、世の中にはまだまだ知られていない、個性豊かで美味しい品種がたくさん存在します。ここでは、そんな珍しいさつまいもと出会うための具体的な方法を3つご紹介します。
道の駅や農産物直売所を探す

旅先やドライブの途中で立ち寄る道の駅や、地域に根差した農産物直売所は、珍しい品種の宝庫です。その土地ならではの伝統的な品種や、試験的に栽培されている新しい品種など、スーパーでは見かけないさつまいもと出会える絶好の機会と言えるでしょう。
生産者である農家さん自らが店頭に立っていることも多く、品種の詳しい特徴や、一番美味しい食べ方を直接教えてもらえるのも大きな魅力です。例えば、「この『くりこがね』は天ぷらにすると絶品だよ」といった、生産者ならではの情報を得られるかもしれません。さつまいもの収穫が本格化する秋から冬にかけて訪れると、品揃えも豊富で、より多くの品種に出会える可能性が高まります。
オンラインストアや産地直送の通販を利用する
近所に直売所がない場合や、特定の品種を探している場合には、オンラインの利用が非常に便利です。全国の農家さんから直接お取り寄せできる産直通販サイトや、各農家が運営するオンラインショップを活用すれば、家にいながら珍しい品種を探し出すことができます。
オンラインストアの利点は、その圧倒的な品揃えです。地域や季節を問わず、様々な品種を比較検討できます。「紅きらら」や「ひめあやか」といった希少品種のほか、複数の珍しい品種を詰め合わせた「食べ比べセット」なども人気があり、自分好みのさつまいもを見つける楽しみが広がります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
家庭菜園で希少品種の栽培に挑戦する

もしあなたが「究極の珍しいさつまいも」を味わいたいなら、家庭菜園での自家栽培に挑戦してみてはいかがでしょうか。市場にはほとんど流通しない品種でも、苗や種芋(たねいも)として販売されていることがあります。自分で育てることで、どんな希少品種でも手に入れる可能性があり、収穫したての新鮮な味は格別です。
さつまいもは病害虫に強く、比較的少ない手間で育てられるため、家庭菜園初心者にもおすすめの野菜です。春に苗を植え付ければ、秋には収穫の喜びを味わえます。ホームセンターや園芸店のほか、オンラインの種苗店では、以下のような珍しい品種の苗が見つかることもあります。
- パープルスイートロード:美しい紫色が特徴で、お菓子作りに最適な品種。
- ハロウィンスウィート:β-カロテンが豊富で、鮮やかなオレンジ色の果肉を持つ。加熱するとかぼちゃのような風味。
- ふくむらさき:他の紫芋よりも甘みが強く、しっとりとした食感が楽しめる新しい品種。
プランターでも十分に栽培可能なため、庭がないご家庭でも気軽にチャレンジできます。自分で育てた珍しいさつまいもの味は、きっと忘れられない体験になるでしょう。
まとめ
「人気がない」と断言できるさつまいも品種は、実は存在しません。時代の食感のトレンドが「ほくほく」から「ねっとり」へと変化したり、加工用など用途が限られていたり、栽培が難しく流通量が少なかったりすることで、店頭で見かける機会が減っているのが実情です。現代では紅はるかなどに代表される甘いねっとり系が主流ですが、これは消費者の好みだけでなく、流通のしやすさや生産の安定性も大きく影響しています。直売所や通販などを利用すれば、料理やお菓子作りに最適な個性豊かな品種にも出会えます。ぜひ様々なさつまいもを味わい、その奥深い魅力に触れてみてください。









