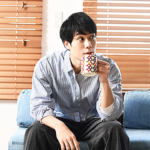「さつまいもは品種が多く、生産地も様々で、どれを選べばいいのか迷ってしまう」と感じている方も少なくないでしょう。特に初心者や普段あまり詳しくない方にとっては、どの品種が自分に合っているのかを判断するのは難しいかもしれません。一般的に、鹿児島県がさつまいもの生産地として広く知られていますが、実際には日本各地でさつまいもが栽培されており、それぞれの地域で特有の品種や特徴があります。今回は、農林水産省が公表している「令和3年度 作物統計」※1をもとに、全国のさつまいもの生産量ランキングを解説し、主要な生産地とその特徴に触れていきます。また、同じく農林水産省が公表している「令和3年度 いも・でん粉に関する資料」※2のデータを参考に、生産地ごとに見られる主要な品種とその特徴もご紹介します。それぞれの地域で栽培されているさつまいもは、味や用途、栽培環境に適応した独自の特徴を持っており、その魅力を知ることで、より自分のニーズに合った品種を選ぶヒントになるはずです。この記事を通じて、主要な生産地の特長や品種に目を向けることで、さつまいもの奥深い世界を知るきっかけとなれば幸いです。自分にぴったりのさつまいもを見つけ、味わいとその背景にある生産地の魅力も合わせて楽しんでみてはいかがでしょうか。
第1位 鹿児島県

さつまいもの生産量ランキングで全国第1位を誇るのは鹿児島県です。その生産量は圧倒的で、190,600トンに達し、全国の生産量の約28.3%を占めています。この数字からもわかるように、鹿児島県はさつまいも栽培の中心地であり、国内最大の供給源としての地位を確立しています。豊かな土壌と温暖な気候が、さつまいもの生育に理想的な環境を提供しており、これが生産量の多さに繋がっていると考えられます。
鹿児島県で主に生産されているさつまいもの品種には、ベニサツマ、コガネセンガン、紅はるかがあります。ベニサツマは、甘みとほっくりとした食感が特徴で、家庭料理や加工食品に幅広く利用されています。一方、コガネセンガンは、デンプン含量が高く、加工用途に特化した品種として知られており、さつまいもチップスや焼酎の原料としても重宝されています。紅はるかは、その名の通り強い甘みとしっとりとした食感が人気で、焼き芋やスイーツなどの用途で全国的に高い評価を受けています。鹿児島県のさつまいもは、地域の気候や土壌条件を最大限に生かして栽培されており、品種ごとに異なる魅力が生まれています。そのため、料理や用途に応じて選べる多様な選択肢があり、消費者の幅広いニーズを満たしています。このように、鹿児島県のさつまいもは品質・量ともに他の追随を許さない存在であり、日本のさつまいも文化を語るうえで欠かせない地域となっています。
ベニサツマの特徴
ベニサツマは、高系14号を元に品種改良して誕生した選抜品種で、さつまいもの中でも独自の特長を持っています。同じ高系14号を基にしたさつまいもとしては、徳島県の鳴門金時や石川県の五郎島金時が挙げられ、これらもまた全国的に高い評価を受けています。ベニサツマの外観は鮮やかな紅赤色で、見るだけで美味しさを想像させる鮮やかさがあります。一方、中身は白っぽい黄色で、甘さの強いさつまいもにありがちな濃い黄色を想像する方にとっては、意外な印象を与えるかもしれません。しかし、外見のイメージとは裏腹に、ベニサツマは非常に強い甘みを持つことが特徴です。

鹿児島県の温暖な気候と肥沃な自然の土壌は、さつまいもの甘みを引き出すために最適な環境を提供しています。そのため、ベニサツマもこの地域の自然の恵みを存分に受けて、甘みがたっぷり詰まった美味しいさつまいもへと育っています。さらに、甘さだけでなく、ホクホクとした食感もベニサツマの大きな魅力です。この食感は、焼き芋にした際に特に際立ち、香ばしい香りとともに口の中で広がる甘みが、焼き芋好きにはたまりません。ベニサツマは、その甘さと食感から、焼き芋をはじめとするシンプルな調理方法で楽しむのにぴったりの品種と言えるでしょう。鹿児島県の自然が生み出したこのさつまいもは、家庭料理だけでなく、多くの人々にとって秋冬の味覚として愛され続けています。
第2位 茨城県

ランキング第2位に位置する茨城県も、さつまいも生産地として非常に重要な役割を担っています。茨城県のさつまいも生産量は189,200トンに達し、その規模は第1位の鹿児島県に匹敵するほどです。この両県だけで、全国のさつまいも生産量の約56.5%を占めており、日本のさつまいも栽培がこの二大産地に大きく支えられていることがわかります。この圧倒的な生産量は、両県が全国的にさつまいもの供給を支える存在であることを物語っています。
茨城県で主に生産されている品種は紅あずまで、この品種は全国的にも非常に人気が高いさつまいもの一つです。紅あずまは、その名前の通り赤い皮が特徴で、焼き芋や蒸し芋にした際の甘さとしっとり感が評価されています。また、調理しても形が崩れにくいため、天ぷらや大学芋、煮物など幅広い料理に適しており、家庭での調理にも重宝される品種です。茨城県は、比較的温暖な気候と適度に砂質を含んだ土壌が広がる地域で、さつまいもの生育に非常に適しています。特に紅あずまは、これらの環境条件を活かして育てられることで、持ち前の甘みと食感を十分に引き出されています。さらに、茨城県内では、長年の栽培技術の向上が図られ、多くの農家が高品質なさつまいもを安定して供給しています。茨城県のさつまいもは、地域の誇りでもあり、多くの人々に親しまれています。その中でも紅あずまは、全国にその名を知られる存在で、茨城県産のさつまいもの代名詞とも言えるでしょう。
紅あずまの特徴
紅あずまは、関東地方を中心に多く栽培されている人気の高い品種です。この品種は、皮色や形状が優れている関東859と、肉質の良さで知られるコガネセンガンを交配して作られました。そのため、外観は非常に美しく、細長い紡錘形と濃い赤紫色の皮が特徴的です。中身はさつまいもらしい鮮やかな黄色で、切り口の色合いが美しいのも魅力の一つです。

紅あずまの食感は、ホクホク感と蜜のようなねっとり感が絶妙に融合した中間型で、さつまいも好きの方々から幅広く支持されています。甘みも十分にあるため、焼き芋にしたときにはその特徴が最大限に引き出され、中身の黄色味がより鮮やかに変化して、見た目にも楽しさを与えてくれます。この視覚的な美しさと、焼いた際の香り、甘さが相まって、焼き芋としての評価は非常に高いものがあります。また、紅あずまは繊維質が少なく、口当たりが滑らかで食べやすいのも大きな魅力です。この特徴から、焼き芋だけでなく、天ぷらや煮物、大学芋といった料理に加え、スイートポテトやパウンドケーキなどのスイーツにも幅広く活用されています。調理の際に形が崩れにくいので、料理の見栄えも良く、食べるだけでなく作る楽しみも提供してくれる品種です。
第3位 千葉県

ランキング第3位に位置する千葉県は、東日本で茨城県に次ぐさつまいもの主要生産地として知られています。千葉県のさつまいも生産量は87,400トンに達しており、その規模は全国的にも重要な位置を占めています。茨城県と同じく、関東地方の温暖な気候と適度に砂質を含む土壌条件が、さつまいもの栽培に適していることが、生産量の多さを支える要因となっています。
千葉県で主に栽培されている品種は、紅あずま、高系14号、ベニコマチです。紅あずまは関東地方全体で広く栽培されている品種で、ホクホクとした食感と甘みが特徴的です。また、焼き芋をはじめ、煮物や天ぷら、スイーツなど幅広い用途に対応するため、消費者からの人気が非常に高い品種です。高系14号は、鹿児島県での栽培が多い品種としても知られていますが、千葉県でも重要な品種の一つです。甘みとともにしっかりした食感が特徴で、加工用としても多く利用されています。千葉県ではベニコマチも生産されており、こちらは小ぶりなサイズとかわいらしい外観が特徴的です。スイートポテトや焼き芋など、スイーツや軽食として楽しむのに適した品種で、甘みが濃厚な点が魅力となっています。こうした多彩な品種の栽培により、千葉県産のさつまいもは、食卓やスイーツ作りにおいて幅広く活用されています。千葉県のさつまいもは、その品質の高さだけでなく、近隣の大消費地である東京や関東圏への流通の良さもあり、多くの消費者にとって身近な存在となっています。豊かな土壌と気候を活かしたさつまいもの生産は、地域の農業を支える重要な柱となっており、今後も安定した供給と新たな品種の開発が期待される産地です。
高系14号の特徴
高系14号は、日本全国で広く栽培されている品種の一つです。このさつまいもは、「ナンシーホール」と「シャム」を交配した後に品種改良を重ねて作られたもので、栽培が始まったのは昭和20年と、非常に歴史のある品種です。その誕生から長い年月が経っていますが、成長が早く、味の良さに定評があるため、現在でも多くの地域で生産され続けています。また、高系14号を基にした品種改良も各地で進められており、この品種がさつまいも栽培の基盤として重要な役割を果たしていることが伺えます。高系14号とその派生品種の作付面積を合わせると、全国のさつまいも作付面積の約12%以上を占めており、この数字からもその人気と生産規模の大きさがわかります。
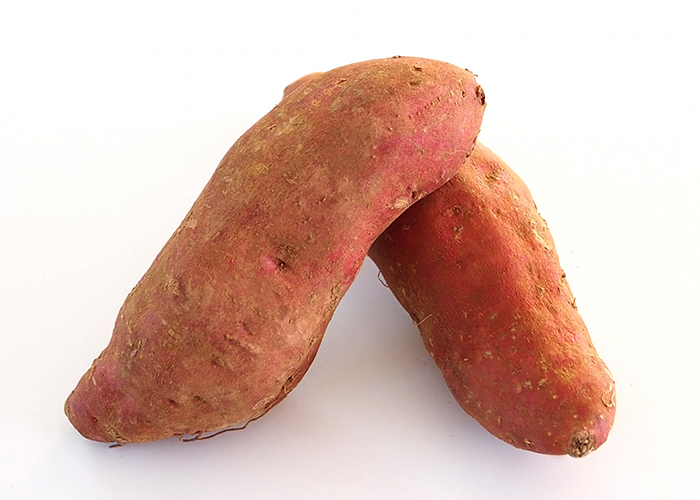
この品種の特徴は、外観の美しさにあります。赤みの強い皮が印象的で、皮には適度な厚みがありながら扱いやすい点が魅力です。中身はクリーム色をしており、ほんのり粉質の食感が特長です。糖度が高く、食感はホクホクとしていて、さつまいも特有の甘さがしっかり感じられます。また、繊維質が少なく口当たりが滑らかなので、焼き芋にすることでその美味しさが最大限に引き出されます。皮が香ばしく焼き上がり、中身のホクホク感と甘みが絶妙に調和して、一口食べるごとに豊かな風味が広がります。焼き芋以外にも、高系14号はスイーツ作りにも適しており、特にスイートポテトなどの滑らかなデザートにすると、その甘さと食感がさらに引き立ちます。家庭でのおやつ作りやパーティーのデザートとしても人気が高く、シンプルな調理法から手の込んだ料理まで幅広く活用できる万能な品種です。
第4位 宮崎県

ランキング第4位の宮崎県は、西日本では鹿児島県に次ぐ重要なさつまいもの生産地として知られています。その生産量は71,000トンに達しており、全国的にも上位に位置する規模を誇ります。温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれた宮崎県は、さつまいもの栽培に適した土壌条件を持ち、多様な品種が栽培されているのが特徴です。鹿児島県に近接する地理的な条件もあり、さつまいも栽培の技術や文化が地域全体に深く根付いていると言えるでしょう。
宮崎県で主に生産されている品種には、コガネセンガン、ムラサキマサリ、シロユタカなどが挙げられます。コガネセンガンは、デンプン含量が高く、焼酎の原料や加工用として全国的に需要のある品種です。甘さとしっかりした肉質が特徴で、加工食品に限らず、天ぷらや煮物にも適しています。一方、ムラサキマサリは鮮やかな紫色の皮と中身が特長で、アントシアニンが豊富に含まれており、健康志向の高まりとともに注目を集めています。鮮やかな色合いからスイーツや料理の彩りを加えるのにも重宝されており、見た目と味の両方で楽しむことができる品種です。シロユタカはその名の通り淡い色合いの外観と滑らかな食感が特長で、さつまいもの中でも特に優しい甘みを持つ品種です。この品種は煮崩れしにくいため、煮物や焼き物に適しており、家庭料理で幅広く活用されています。宮崎県のさつまいもは、多様な品種とその特性を活かした用途の広さが魅力で、地元だけでなく全国各地で親しまれています。地域の気候風土を活かした栽培方法と、長年培われてきた農家の技術によって、高品質なさつまいもが生産されており、西日本における重要な供給源となっています。
コガネセンガンの特徴
コガネセンガンは、主に鹿児島県や宮崎県で栽培されている品種で、長い歴史を持つさつまいもの一つです。鹿系7-120とL-4-5という品種を交配して育成され、昭和41年に品種登録されました。その名前は、皮の色がじゃがいものような黄金色であること、さらに収穫量が多い品種であることから名付けられています。農家にとって栽培しやすく、生産性が高いことから広く普及し、地域の農業を支える重要な品種として知られています。

もともと、コガネセンガンは焼酎やでんぷんの原料として活用されることを目的に開発されました。その理由は、この品種がデンプン含量に優れていること、そして収穫量の多さが加工用に適しているためです。しかし、その後、でんぷん質の多さや優しい甘み、ホクホクとした食感が評価され、天ぷらやスイーツの材料としても使われるようになりました。揚げ物やスイーツにすることで、コガネセンガン特有の粉質感が活き、料理全体に軽やかで上品な風味を与えてくれます。ただし、粉質感が強いため、焼き芋にする場合にはパサつきを感じることがあり、その点では焼き芋向きの品種とは言えないかもしれません。コガネセンガンは芋焼酎の原料としても高い評価を受けています。この品種を使用して作られた芋焼酎は、程よい芋の香りが感じられる上品な味わいが特徴で、口当たりが滑らかで飲みやすい仕上がりとなっています。そのため、焼酎好きだけでなく、焼酎初心者にも親しまれている銘柄が多く、コガネセンガンは日本の焼酎文化にも欠かせない存在となっています。
まとめ

今回は、さつまいもの生産量ランキングを通じて、各地域で生産されているさつまいもの特長を詳しくご紹介しました。さつまいもの生産は、関東圏と九州地方を中心に特に盛んで、それぞれの地域に適した主要品種が栽培されています。これらの品種は、その地域の気候や土壌に適応しながら独自の特性を持っており、食感や甘さ、用途に応じた選び方が楽しめる点が魅力です。例えば、関東地方では紅あずまが広く栽培されており、ホクホク感としっとり感のバランスが良く、焼き芋やスイーツに適しています。一方、九州地方では鹿児島県を中心にコガネセンガンや紅はるかといった品種が栽培され、それぞれ甘さや食感に独自の個性を持っています。地域や品種による違いを知ることで、さつまいもの選び方がより楽しくなり、調理や料理の幅も広がるでしょう。今回ご紹介したように、さつまいもには地域や品種ごとにさまざまな魅力が詰まっています。それぞれの特性を知り、適切な調理法で楽しむことで、さつまいもの美味しさを存分に引き出すことができます。次回の食材選びでは、さつまいもの品種や生産地に注目して、新たな選び方でさつまいもの楽しみ方を試してみてはいかがでしょうか。
<参考資料>
※1 農林水産省「令和3年度 作物統計」
※2 農林水産省「令和3年度 いも・でん粉に関する資料」